適応障害|退職の判断基準や流れを解説!利用できる支援制度・サポート機関を紹介

仕事が原因で適応障害を発症した場合、退職を考える人もいます。退職後の生活や再就職の不安は、誰にとっても大きなプレッシャーです。この記事では、適応障害で退職する前にできることや手続き、利用できる支援制度を解説します。記事を読めば、適切な判断ができ、新しい人生のスタートを切るヒントが得られます。
適応障害は仕事や人間関係など、現代社会のストレスの中で多くの人が直面する深刻な課題です。適切な準備と支援を受けて、人生の新たなステージに進みましょう。
適応障害で退職するのは逃げではない

適応障害による退職は、自分の健康と幸福を守るための勇気ある決断です。自己を見つめ直し、新たな機会を探すチャンスでもあります。サポート制度を活用し、再就職に向けて準備を進めましょう。
適応障害で退職する前にできること

適応障害で退職を決断する前に、以下の選択肢を検討してください。
- 医師に相談する
- 上司に相談する
- 休職を検討する
医師に相談する
症状の改善や今後の方針を決めるため、医師との相談が大切な役割を果たします。医師に相談する際は、自分の症状や状況を詳しく説明し、適応障害の診断を受けます。治療方針や休職・退職の必要性についても医学的見解を求めましょう。
医師との相談で、薬物療法やカウンセリングなどの適切な治療方法を見つけられます。定期的な通院スケジュールを立て、医師との信頼関係を構築しましょう。
上司に相談する

上司に相談して正直に状況を伝え、サポートを求めましょう。解決のきっかけが得られる場合があります。以下の内容を相談すると効果的です。
- 現在の症状や困っている点
- 業務内容や環境の改善の可能性
- 休職や配置転換の選択肢
- 会社の制度や支援策
自分の状況を客観的に説明し、改善案や要望を伝えてください。医療機関での受診結果を報告し、必要な配慮を依頼すると効果的です。上司の理解とサポートを得られると、職場に適応しやすくなります。上司との相談だけで解決が難しい場合は、人事部門への相談も検討してください。
継続的にコミュニケーションを取れば、状況の変化に応じた対応が可能です。退職を検討している場合は、退職の意向を率直に伝えましょう。
休職を検討する
休職は、適応障害からの回復と職場復帰を目指すための重要な選択肢です。休職を検討する際の手順は、以下のとおりです。
- 人事部門に相談する
- 給与や社会保険について確認する
- 休職期間を設定する
- 休職中の計画を立てる
休職中は自分自身と向き合い、ストレス管理や生活リズムの改善に取り組みます。職場復帰に向けたスキルアップや自己啓発の計画も効果的です。休職を決断する前に上司や人事部門と相談し、会社のサポート体制や復帰プログラムの有無を確認してください。
» 仕事が怖い!適応障害の主な症状と対処法
休職中の連絡方法や頻度についても事前に話し合いましょう。経済面に不安がある場合は、休職期間中の生活設計を立ててください。家族や周囲にサポートを求めると、安心感を得られます。十分な治療と休養を取れば、職場復帰後により良いパフォーマンスを発揮できる可能性が高まります。
» 適応障害で休職すべきケースと手続き方法を解説!
適応障害で退職するときの流れ

適応障害で退職を進める際には、以下の流れを参考にするとスムーズです。
- 医師や産業医からの診断を受ける
- 上司や人事に退職の意思を伝える
- 退職届を提出する
医師や産業医からの診断を受ける
適応障害で退職を考えている場合、医師や産業医からの診断を受けることが重要です。自分の状態を客観的に把握し、適切な対応を取れます。
診断を受ける際の流れは、以下のとおりです。
- 主治医から診断を受ける
- 診断書を取得する
- 産業医の面談を受ける
- 意見書を取得する
診断書には休職期間や治療経過、現在の症状を詳しく記載してもらいます。診断書と意見書を入手後、人事部門に提出します。主治医や産業医との診断や意見書をもとに、今後の方針を慎重に検討しましょう。
上司や人事に退職の意思を伝える

上司や人事に退職の意思を伝える際には、以下の手順に沿って進めるとスムーズです。
- 退職理由を明確に説明する
- 具体的な退職希望日を伝える
- 引き継ぎ計画を相談する
- 感謝の気持ちを伝える
体調不良や回復を目指す意向を率直に話すと理解を得やすくなります。退職希望日は会社の規定や引き継ぎ期間を考慮しながら提案してください。
退職届を提出する
退職届を作成する際は、日付や宛先、本文や署名を正確に記載し、退職理由は簡潔にまとめましょう。詳細の説明は口頭で伝えてください。退職日も明確に記載し、テンプレートを活用すれば形式的なミスを防げます。作成した退職届は、上司や人事部門に直接手渡してください。
退職後の手続きや引き継ぎについて確認しましょう。退職届はコピーして保管します。提出後は、会社の規定に沿って退職手続きを進めてください。引き継ぎ作業への注力も大切です。
適応障害で退職した後にやるべきこと

適応障害で退職後に充実した生活を送るために、以下の行動に取り組みましょう。
- 健康保険と年金の切り替え手続きをする
- 健康的な生活を送る
- 再就職活動を始める
健康保険と年金の切り替え手続きをする
退職後の生活を守るため、健康保険と年金の切り替え手続きは重要です。国民健康保険への加入と国民年金への切り替えは市区町村の役所で手続きします。健康保険任意継続制度を利用すれば、退職後2年間は加入していた健康保険を継続できます。
配偶者の健康保険に加入できる場合は、被扶養者の手続きも選択肢の一つです。忘れずに年金手帳を確認して、大切に保管しましょう。国民年金保険料の納付方法には、口座振替やクレジットカード払いがあります。経済的に困難な場合は、免除・猶予制度の利用を検討できます。ねんきんネットでの年金記録の確認も重要です。
前の勤務先に健康保険証を返却し、新しい健康保険証を受け取った際は内容を確認しましょう。不安があれば、市区町村の窓口で相談してください。
健康的な生活を送る

規則正しい生活リズムを確立し、バランスの取れた食事と適度な運動を心がけましょう。十分な睡眠時間を確保し、ストレス解消法を見つけることも重要です。趣味や楽しみを見つけ、心の健康を保ちましょう。社会とのつながりを維持し、孤立を避ける姿勢も重要です。
定期的に医療機関を受診し、自己肯定感を高める活動をしましょう。リラックス法を学び、実践により心身のバランスを整えてください。アルコールやカフェインの摂取も控えましょう。瞑想やヨガなどのマインドフルネス活動を取り入れると心の安定に役立ちます。
再就職活動を始める
再就職活動は適応障害から回復し、心身の状態が安定してから少しずつ始めましょう。自己分析で過去の経験や強み、やりたいことを整理します。履歴書やエントリーシートを準備し、経歴や志望動機をわかりやすくまとめましょう。
求人情報を集めるには、ポータルサイトやハローワーク、人脈の活用が有効です。必要に応じて職業訓練や資格取得を検討しましょう。新しいスキルを身に付ければキャリアの幅を広げられます。面接対策も大切です。適応障害の経験を前向きに捉え、自己成長をアピールできるよう準備しましょう。
» 適応障害からの復職後にしんどいときの対処法&相談先
在宅勤務や時短勤務など柔軟な働き方も検討してください。自分に合った働き方を探すと再発リスクを減らせます。企業の福利厚生や社風をよく調べ、自分に合った環境を見つけることが大切です。必要に応じて就労支援サービスを利用し、専門家のサポートを受ければ効果的な再就職活動が進められます。
» 適応障害の方向け!対処法と仕事探しのポイントを解説!
適応障害で退職した後に利用できる経済的支援制度

適応障害で退職後の生活を支えるために、以下の経済的支援制度を活用できます。
- 傷病手当金
- 失業手当
- 自立支援医療
- 障害年金
- 生活保護
傷病手当金
傷病手当金は、適応障害などで働けなくなった際に利用できる経済的支援制度です。療養中の生活を支える助けになります。健康保険の被保険者であれば、病気やけがが原因で働けない場合に受給が可能です。支給期間は最長1年6か月で、支給額は直近12か月の平均給与日額の3分の2に相当します。
支給は、連続して3日間仕事を休んだ後の4日目から始まります。適応障害も傷病手当金の対象となる場合はありますが、医師の診断書が必要です。退職後も一定の条件を満たせば、最長18か月間受給が可能であり、療養に専念しやすくなります。
会社員の場合は会社を通じて手続きをして、国民健康保険では保険者に直接手続きします。傷病手当金は、雇用保険の失業給付と同時には受け取れません。傷病手当金は課税対象となるため、申請時には注意が必要です。
失業手当

失業手当は離職後の生活を支え、再就職を促進するための制度です。適応障害で退職した場合でも、条件を満たせば受給できます。受給するには、離職前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です。給付日数は年齢や離職理由により90~360日まで異なります。給付額は離職前の賃金の50〜80%です。
受給には、ハローワークでの求職申し込みと失業認定が必要です。受給期間は、原則として離職日の翌日から1年以内となります。病気やけがで就職が難しい場合は、最大3年まで延長できるケースがあります。適応障害で就職活動が難しい場合は、延長制度の利用をハローワークに相談しましょう。
自己都合退職の場合は3か月の給付制限期間があるため注意が必要です。適応障害による退職が会社都合と認められると、制限が適用されない場合もあります。再就職手当や教育訓練給付金など、再就職を支援する制度もあるので、活用を検討しましょう。
自立支援医療
自立支援医療は、適応障害などの精神疾患における医療費負担を軽減する制度です。医療費の自己負担額が原則1割になります。所得に応じた自己負担上限額が設定され、通院医療費や薬代も対象です。対象は18歳以上65歳未満で、有効期間は1年間ですが、更新可能です。
申請には医師の診断書を準備し、市区町村の窓口で手続きをします。精神障害者保健福祉手帳の取得は不要ですが、所得制限があります。転職後も利用できますが、再申請が必要な場合があるため注意が必要です。経済的負担を軽減しながら、必要な治療を受けられます。
障害年金

障害年金は、適応障害などで働くことが難しくなった人を経済的に支える制度です。初診日から1年6か月後に請求可能で、長期的な支援が必要な場合に役立ちます。適応障害は主に2級または3級に該当する可能性があります。支給額は障害の程度によって異なり、申請には医師の診断書が必要です。
20歳以上は国民年金から、会社員は厚生年金から支給されます。受給には以下の手続きが必要です。
- 医師の診断書を提出する
- 就労状況などを証明する
- 定期的に診断書を再提出する
- 現況届を提出する
障害年金を受給しながらの就労も可能です。収入制限はありますが、症状が改善しても一定期間は受給が継続されるため、再就職への不安が軽減されます。
生活保護
生活保護は、収入や資産が基準以下の人に最低限の生活を保障する公的扶助制度です。生活保護には、医療費の負担を軽減する医療扶助があります。生活費を補助する生活扶助や住居費を支援する住宅扶助も含まれています。居住地の福祉事務所で申請できますが、厳格な審査が必要です。
就労可能と判断された場合は求職活動が求められます。受給中は、収入や資産の定期報告が必要です。生活保護は、適応障害からの回復と自立を目指すための一時的な支援として活用可能です。社会的な偏見があるため慎重に検討しましょう。他の支援制度の優先的な利用がおすすめです。
適応障害で退職した人の再就職をサポートする機関・制度

適応障害で退職後、新たなキャリアを築くためには、以下のサポート機関や制度を活用しましょう。
- ハローワーク
- 精神保健福祉センター
- 就労移行支援
ハローワーク
ハローワークは、適応障害で退職した人の再就職を支援する機関です。無料の職業紹介サービスを提供しており、以下のサポートが受けられます。
- 求人情報の提供
- 職業相談・職業指導
- 就職支援セミナー
- 障害者向け専門窓口
障害者向け専門窓口では、就労支援ナビゲーターによる個別支援を受けられます。状況に合わせたサポートが得られるため、安心して利用可能です。ハローワークでは職場実習を斡旋し、実務経験を通じて自信を取り戻せます。就職後もフォローアップがあり、適応障害からの回復を目指す人をサポートします。
精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは、適応障害で退職した人の再就職を支援する機関です。専門的な支援を受けられるため、安心して利用可能です。相談サービスや就労支援プログラム、社会復帰プログラムも提供されています。
精神保健福祉相談員や保健師、医師などの専門スタッフが在籍しており、適切なアドバイスを受けられます。電話相談や面接相談が可能なため、自分に合った方法で利用可能です。地域の医療機関や福祉施設とも連携しており、総合的なサポートを提供しています。
就労移行支援
就労移行支援は、障害のある人が一般就労を目指せるようサポートする制度です。利用期間は原則2年間で、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つです。就労に必要な知識や能力の向上を支援するため、以下のサポートを受けられます。
- 職場体験や実習
- 就職活動のサポート
- 職場定着支援
- 実践的な訓練
- グループワーク
専門スタッフが個別支援計画を作成し、一人ひとりに合わせた支援を提供します。就職後のフォローアップや、長期的な就労サポートも可能です。利用には障害者手帳または医師の診断書が必要です。利用料は原則1割負担ですが、所得に応じた上限があります。
全国に多くの事業所があるため、地域で利用できる可能性が高まります。専門家のサポートを受けながら、自分のペースで就労準備を進められる点が大きな特徴です。
まとめ
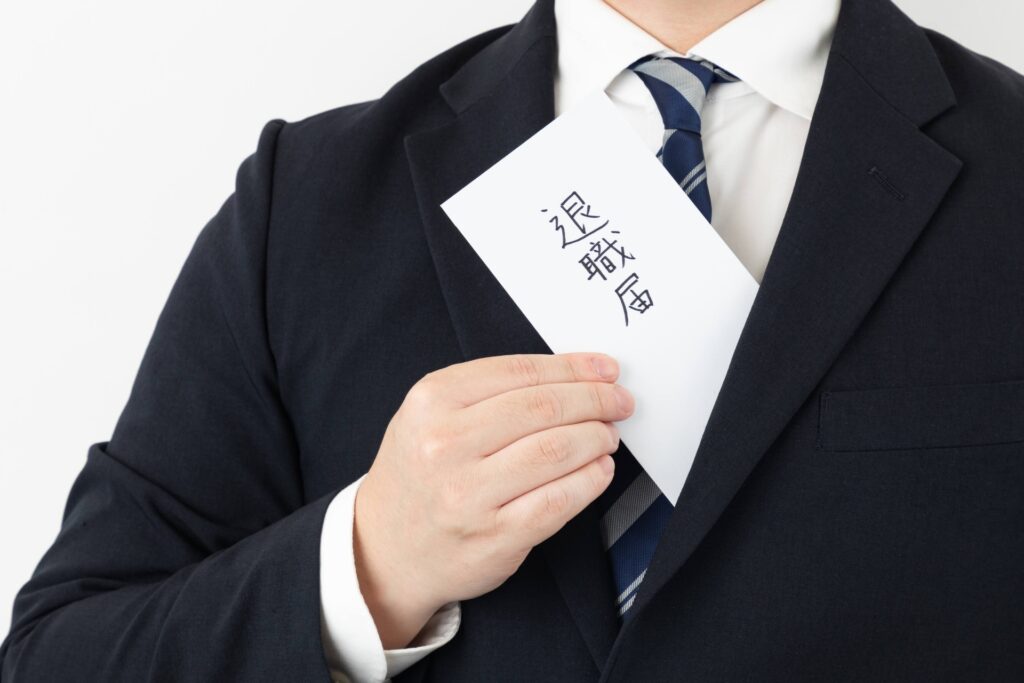
適応障害による退職は、自分の健康を守るための大切な決断です。退職前に医師や上司に相談し、休職の検討を含む選択肢を探りましょう。退職後は健康保険や年金を切り替え、心身の回復に努めることが重要です。経済面では、傷病手当金や失業手当などを活用できます。
再就職に向けては、支援機関を利用し、自分のペースで準備を進めましょう。焦らず、周りのサポートを受けながらの前進が大切です。






